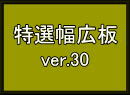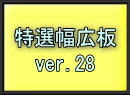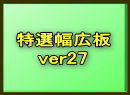益子林業のブログ
-
何故KD材の管柱が曲がってしまうのか 2025.08.25
-
とちぎ八溝杉を製材・販売する益子林業です。
前回の後半で、仕入れをした杉KD材の管柱3000×105×105を2ヶ月~5ヶ月在庫して寝かせておくと、10%~15%は曲がりが大きくて管柱としては使えないものが発生してしまうと申しました。


実は間柱はもっと多くて、15%~25%は間柱として使えない曲がり材が発生します。この原因を考察してみましょう。
その前に、使えない曲がりの基準は益子林業では製品を真直ぐな定規にくっつけたときに、中央部に出来る隙間が3㎜以下なら合格、3㎜以上なら不合格としています。


では3㎜ちょうどはどうかと言われると、そもそもそこまで厳密に計れないので、担当者の判断にに委ねます。
もしかするといい加減と思われるかもしれませんが、私はここまで検品をしてから出荷している材木屋を知りません。なので、かなり厳格な検品をしているとご理解ください。
益子林業から出荷する管柱には殆どの場合、刷版(スリバン)を入れます。


刷版の内容(文字など)はお客様と打ち合わせして決めますが、刷版を入れる一番の目的は全量検品を行ったという証なのです。
お客様(工務店様)から、建て方時に施主から刷版について質問を受けることが多いと聞いてます。
その時に、この現場に使われている管柱はプレカットする前に全量検品をして直材のみを使用していると説明するそうです。
話しは戻って曲がりの原因ですが、大きく分けて3つの理由があります。
一つ目は原木の素性、2つ目は製材方法、3つ目は乾燥方法です。
まだ、芯付き管柱の背割り無しKD材が存在しなかった時代、天然乾燥で管柱を作っていましたが、曲がってしまうとその製品の評価が下がります。
したがって製材工場は曲がらない管柱を作るために、素性の良い原木を仕入れることからスタートしていました。
益子林業でもこの時代は管柱を製材していましたから、この理論は実証済みです。
かと言って、100%素性の良い原木のみを仕入れることは不可能です。
どんな良材の山にも素性の悪い原木は存在します。
それを見極めて木取を変えていました。
木取とは原木から角材を採るのに、原木の芯が製品の中心になるように挽いたり、あえて芯をずらして挽いたりすることです。
これによって、後々の曲がり具合をコントロールすることが出来ました。
やがて、ドライングセットによる背割り無しのKD材の時代になり、少々素性の悪い丸太からでも曲がりの少ないKD材の製品を作れるようになりました。
しかし、杉は原木の時点で個々の含水率にばらつきがあったり、同じ初期含水率でも乾きやすい個体があったり、乾きにくい個体があるため、同じ乾燥スケジュールで窯出し時含水率を揃えることは出来ません。
そこで2つの方法が考えられました。一つ目は、1次製材直後に初期含水率を測定し、ばらつきのある乾燥前の製品を仕分けして、ある程度同じ含水率のもの同士で窯入れする方法です。
しかしこの方法にもデメリットがあり、現在この方法を行っている工場は稀だと思います。
二つ目は、乾燥スケジュールを初期含水率の高い、そして乾きにくいものに合わせて行い、乾燥最終工程で調湿(蒸気をかて製品に湿気を吸わせる)を乾燥機内で行い、窯出し時点での含水率を均一化する方法です。現在は殆どの工場がこの方法でKD材を作っていると思います。
ところが、さらに養生期間を十分に取らないと角材の内部での含水率に偏り(水分傾斜)があるため、すぐに2次製材(モルダー加工)してしまうと、そこからまた曲がってしまう製品が出てしまいます。
つまり、曲がらないKD材を作るためには、窯出し後さらに2ヶ月以上の養生期間を取る必要があると思われます。
しかし、量産工場で2ヶ月分の製品を在庫するのは、それ相応の場所と資金が必要になります。
ということで、現在の杉KD管柱製材工場の状況から判断すると今以上のレベルの製品を作るのは、かなり難しいのではないでしょうか。
そうなると、プレカット工場や材木店が在庫をしながら製品が落ち着くまで待って、それを仕分けして使うことが現状ではベストではないかと思っています。
ですから、仕入れをして即座に検品もせずにプレカットして納品するのは、如何なものかと思います。
ちなみに管柱に使えない曲がり材は、束、桁、母屋へと回します。
弊社の場合こうして使えば、殆ど無駄なく使い切ることが出来ています。材木納材者はこの程度の手間をかけても良いのではないでしょうか。
いずれにしても、これを読んでいただいている建築家の皆様は、現在の杉KD管柱の現状とレベルをご理解いただき、上手に国産材をご利用頂ければ幸いです。